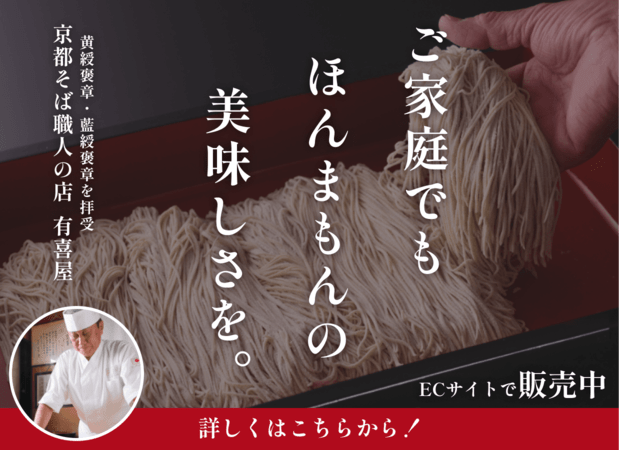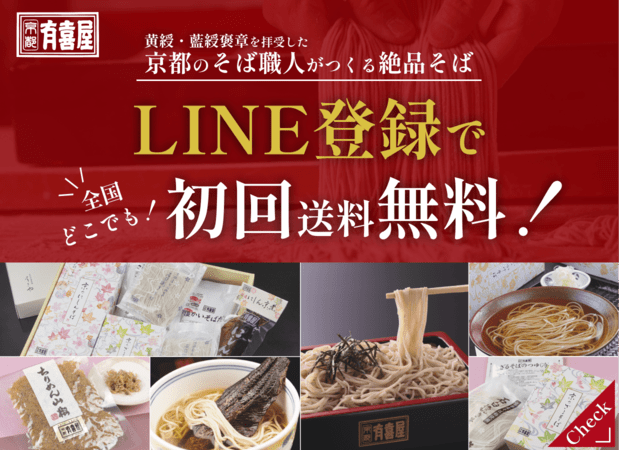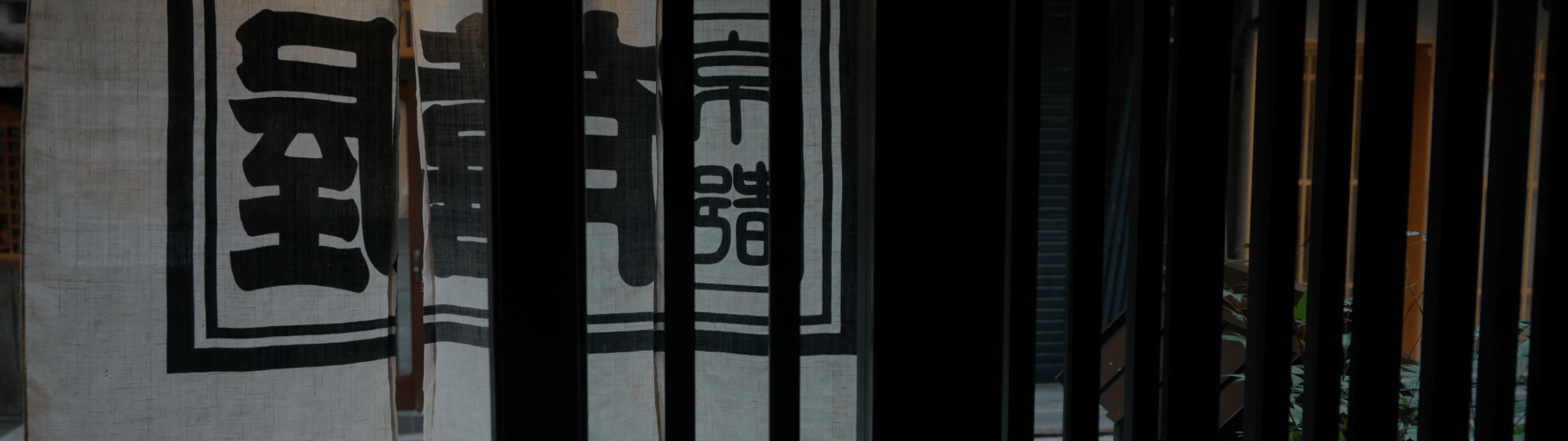
COLUMN
コラム
「そばは消化に悪い」は本当?その理由と体に優しい食べ方のコツを解説

この記事の監修者

有喜屋 三代目店主
三嶋吉晴
有喜屋(うきや)三代目店主。有喜屋は1929年 京都先斗町に創業した本格手打ちそばと蕎麦料理を提供するそば屋です。 最年少で京都府優秀技能者表彰「京都府の現代の名工」を受彰。 手打そば職人としては全国で初となる「卓越技能章」を厚生労働大臣より受彰。 天皇陛下から授与される褒章である、「黄綬褒章」を拝受。
「そばって消化に良いの?それとも悪いの?」
「体によりやさしくそばを食べる方法が知りたい」
そばは消化に良いイメージを持つ人も多い食品ですが、その一方で「消化に悪い」という意見もあり、どちらが正解なのかわからないという方も少なくありません。
そこでこの記事では、「消化に悪い」と言われる理由を解説し、さらに消化を良くするための具体的な5つのコツも紹介します。
オンラインショップで極上のそばを販売中!
目次
1.そばは消化に良い?悪い?
そばはビタミンB群やルチンなどの栄養素が豊富で、ヘルシーな低GI食品として知られています。そのため「健康や美容に良い」という印象を持つ人が多い食品です。しかしながら、「消化に良い」とは言い難い面があります。
見た目や口当たりはあっさりしており、脂質も少ないため、一見すると胃に優しそうに思われがちです。実際、油分が少ないことから、うどんやラーメンに比べて胃への負担は軽く感じる場合もあります。
しかし、そばは穀物の中でも食物繊維が多く、たんぱく質の構造もやや複雑であるため、消化には時間がかかります。また、そば粉には消化酵素で分解しにくい成分も含まれており、胃腸が弱い人にとっては「消化に悪い食べ物」といえます。実際に、「そばを食べたらお腹の調子が悪くなった」「重く感じた」といった声も少なくありません。
2.「そばは消化に悪い」と言われる理由
そばはヘルシーで胃腸にやさしい面がある一方、そばの種類や食べる人の体調や食べ方によっては、かえって胃腸に負担をかけてしまい消化に悪くなってしまうケースもあります。
次に、そばが「消化に悪い」と言われる理由をわかりやすく解説します。
- 不溶性食物繊維が豊富で消化に時間がかかる
- そば通の粋な食べ方が負担となることがある
- 冷たいそばで内臓が冷やされる
(1)不溶性食物繊維が豊富で消化に時間がかかる
そばが「消化に悪い」と言われる理由のひとつは、不溶性食物繊維を多く含んでいるためです。
食物繊維は腸内環境を意識するうえで注目される成分で、大きく次の2種類に分けられます。
- 水溶性食物繊維:水に溶けやすく、腸内で水分を含む性質を持つ。
- 不溶性食物繊維:水に溶けにくく、便のかさを増やす性質がある。
そばには後者の不溶性食物繊維が多く含まれており、水に溶けずにゆっくりと胃腸を通過するため、消化に時間がかかることがあります。これが「消化に悪い」と言われる要因のひとつです。
ただし、こうした特徴は体の調子や食べる量によって感じ方が異なります。胃腸の調子がすぐれないときは少量にするなど、体調に合わせた食べ方を心がけると良いでしょう。
(2)そば通の粋な食べ方が負担となることがある
そば通の中では、のどごしや香りを楽しむために「そばは途中で噛み切らず、すすって一気に食べること」が粋とされています。
しかし、そばに限らず、食材をよく噛まずに食べることは胃に負担をかけることになります。噛む回数が少ないと、唾液の中に含まれる消化酵素としっかり混ざらないまま食べ物が胃に送られるため、胃での消化に時間がかかり、負担をかけてしまうためです。
特に胃腸が弱い人がそばをよく噛まずに食べると、胃もたれや重さを感じやすくなります。そのため「消化に悪い」と感じることが多いのです。
そば通の食べ方については次の記事をご覧ください。
▸知っておきたいそばのマナー|粋な食べ方やそば湯の飲み方を解説
(3)冷たいそばで内臓が冷やされる
暑い季節の定番であるざるそばなどの冷たいそばは、さっぱりしていて食欲が落ちやすい時でも食べやすいのが魅力です。一方で、冷たい食事は体を内側から冷やしやすく、人によっては食後にお腹の張りや重さを感じることがあります。
特に胃腸がデリケートな方や冷えを感じやすい方は、体調によって負担を感じる場合もあるため、温かいそばを取り入れたり、常温の飲み物を合わせるなどの工夫もおすすめです。
3.そばの消化を良くする5つのコツ
栄養豊富でヘルシーなそばですが、体調や食べ方によっては胃腸に負担をかけて消化が悪くなることもあります。そこで、そばを美味しく、かつ消化に良く食べるためのポイントを5つご紹介します。
- ゆっくりよく噛んで食べる
- そば粉の配合量が少ないそばを選ぶ
- あたたかいそばを選ぶ
- 消化に良いトッピングと一緒に食べる
- そば湯をたっぷり飲む
(1)ゆっくりよく噛んで食べる
そばを胃腸に負担をかけずに食べるには、しっかりよく噛んで食べることが効果的です。
すすってあまり噛まないそば通の食べ方も粋でおしゃれですが、体にやさしく食べることが何よりも大事です。そばの味や香りの広がりを楽しみながらしっかり噛んで食べて唾液としっかり混ぜることで胃の負担を減らし、消化をサポートしましょう。
(2)そば粉の配合量が少ないそばを選ぶ
そば粉の配合量が多いほど、含まれる不溶性食物繊維の量も多くなります。
具体的には100%そば粉で作られた十割そばや全粒粉であらびきの田舎そばよりも、小麦粉などのつなぎがはいった二八そばや、胚乳だけを使った更科そばのほうが不要性食物繊維量も少なく消化しやすいです。
そばを食べたときに胃腸の負担が気になる方は、そば粉の配合量が少ない種類を選ぶのがおすすめです。
そばの種類についてさらに詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
▸十割そばとは?読み方や魅力・二八そばとの違いを徹底解説!
▸そばの種類を分類別に紹介!手打ちそばからにしんそばまで
(3)あたたかいそばを選ぶ
冷たいそばは内臓を冷やしてしまうため胃腸の働きを弱めるおそれがあるため、消化が気になる方は、できるだけ温かいそばを選ぶのがおすすめです。温かいそばは胃腸を冷やさず、消化酵素の働きも妨げられないため、胃もたれや腹部の不快感を軽減しやすくなります。
(4)消化に良いトッピングと一緒に食べる
そばをよりおいしく、体にやさしく楽しむには、食材の特徴を生かしたトッピングを組み合わせるのも一案です。たとえば次のような食材がよく使われます。
- 大根おろし:さっぱりとした風味で、食後も軽やかな印象に
- とろろ:ねばり成分が特徴で、なめらかな食感がそばとよく合う
- わかめ:水溶性食物繊維を含み、ヘルシーな印象のトッピングとして人気
- ねぎ:香りと辛味がそばの味を引き立て、アクセントに
- うめぼし:酸味が食欲をそそり、さっぱりとした後味
また、体調がすぐれない時や胃に負担を感じやすい時は、揚げ物など油の多いメニューを控えめにして、軽めのトッピングを選ぶのも良いでしょう。
(5)そば湯をたっぷり飲む
食後にそば湯を味わうのは、そばをより楽しむための習慣のひとつです。そば湯には、そばをゆでる際にお湯へと溶け出した成分が含まれており、まろやかな風味を楽しめます。
また、不溶性食物繊維は水分と一緒にとることでスムーズに体を通りやすくなるといわれています。食後の水分補給としてそば湯を取り入れるのもおすすめです。
あたたかいそば湯をゆっくり味わうことで、食事の締めくくりとしてほっと一息つけるのも魅力です。
そば湯の飲み方や栄養についてさらに詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
▸そば湯を飲む理由とは?そば湯の飲み方・注意点やそば湯の歴史を解説
体に優しくおいしいそばを有喜屋でどうぞ
そばは栄養豊富でヘルシーな食品として知られていますが、体調や食べ方によっては消化に負担をかけてしまうこともあります。しかし、食べ方を一工夫することで胃腸への負担を軽減し、より快適に体に優しくそばを楽しむことができます。
有喜屋では、熟練のそば職人が手打ちそばを作っており、十割そばや二八そばなどを提供しています。さらに、ご家庭でも有喜屋のそばを召し上がっていただけるように、オンラインショップで乾麺そばも販売しています。そばの風味とコシを楽しめる有喜屋の乾麺そばを、この機会にぜひご賞味ください。